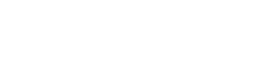-
法定相続分と遺留分の違い(酒井)|岡崎市の税理士事務所

山本富彦税理士事務所/株式会社アンドリュウ
スタッフお役立ちブログ
staff useful blog
法定相続分と遺留分の違い(酒井)
2025.07.30
梅雨も明け、本格的な夏を迎えましたがいかがお過ごしでしょうか。
今回は「法定相続分」と「遺留分」の違いについて解説します。
この2つは内容が似ているようで実はまったく役割が異なります。
①法定相続分とは?
まずは「法定相続分」について説明します。
法定相続分とは、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの民法で定められた遺産の持分となります。
ただし、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
これはあくまで基準にすぎず、遺言書があればそれに従うのが原則となります。
②遺留分とは?
一方、「遺留分」は、最低限相続できると保証された遺産の割合のことです。
つまり、遺言で法定相続分が無視されても、完全に取り分がゼロになるのを防ぐ「最後の砦」となるのが遺留分です。
遺留分は、すべての相続人にあるわけではなく、
配偶者、子ども(またはその代襲相続人)、直系尊属(子や配偶者がいない場合のみ)が対象となりますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
③内容の比較
| 比較項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 定義 | 民法で定められた基本的な相続の取り分 | 最低限保証された相続の取り分 |
| 強制力 | 遺言によって変更可能 | 遺言でも奪えない(請求できる) |
| 対象者 | 相続人全員 | 配偶者・子・直系尊属など一部の相続人 |
| 主な使い道 | 遺産分割協議の基準 | 不公平な遺言に対する防御策 |
《割合》
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 1(全部) | 1/2 |
| 配偶者と子 | 配偶者1/2・子1/2 | 配偶者1/4・子1/4 |
| 子のみ | 1(全部) | 1/2 |
| 配偶者と
直系尊属 |
配偶者2/3・直系尊属1/3 | 配偶者1/3・直系尊属1/6 |
| 直系尊属
のみ |
1(全部) | 1/3 |
| 配偶者と
兄弟姉妹 |
配偶者3/4・直系尊属1/4 | 配偶者1/2・兄弟姉妹なし |
④遺留分を侵害された場合
遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」という手続きで、その分を請求することができます。
ただし、相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内、又は、相続開始から10年以内でなければ請求できなくなるので注意が必要です。
相続の場面では、「法定相続分」と「遺留分」がそれぞれ重要な役割を果たします。
・法定相続分は「原則のルール」
・遺留分は「最低限の保障」
相続トラブルを避けるためにも、早めに遺言書を作成したり、家族で話し合っておくことが大切となりますので、早めに準備をしておきましょう。
山本富彦税理士務所&株式会社アンドリュウ
相談料 30分 ¥5,500(税込み)
心配していること、悩んでいることを相談してみませんか?
TEL 0564-55-3320 https://x-yz.jp/
prev.
相次相続控除(村松)
next.
遺言書に記載されていない財産(鈴木)
RECOMMEND
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。
NEW POST
-
2026.01.21
不動産を相続したら(村松)
-
2026.01.07
相続(税)対策は何歳から考えるべき?(小出)
-
2025.12.18
2025年最後のブログ(EIKO)
CALENDAR
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
copyright(c) 2011 tomihiko yamamoto TAX ACCOUNTANT OFFICE | ANDRYU CO.,LTD All Rights Reserved.